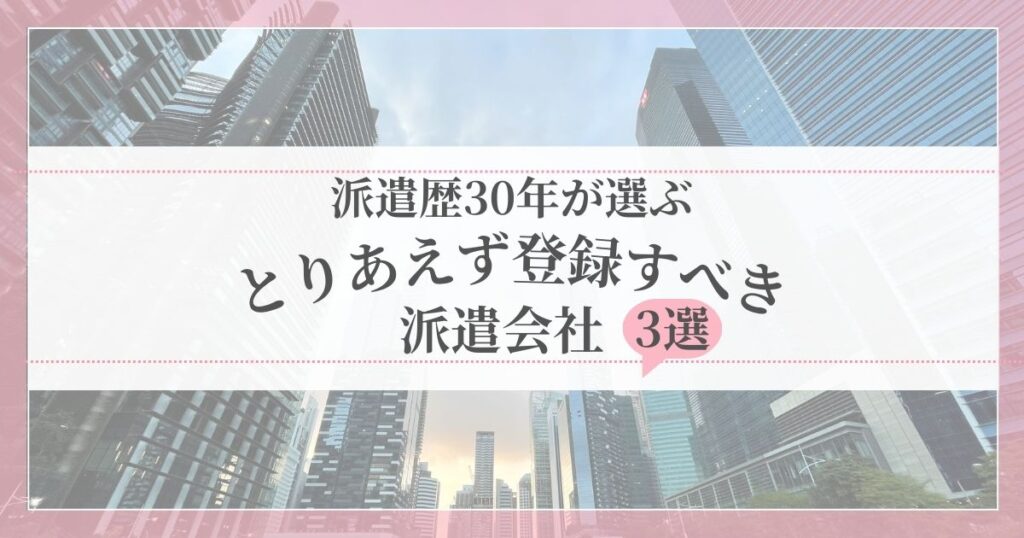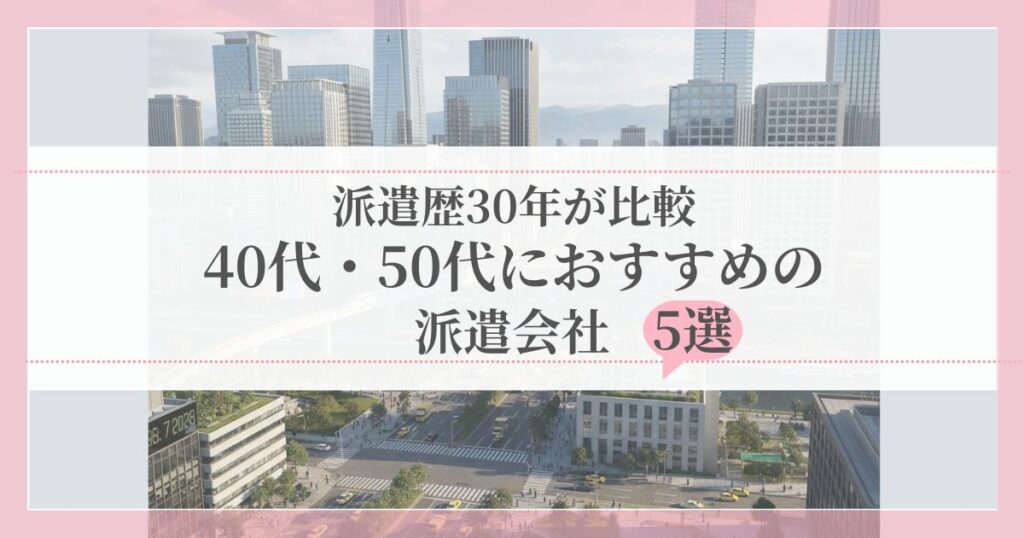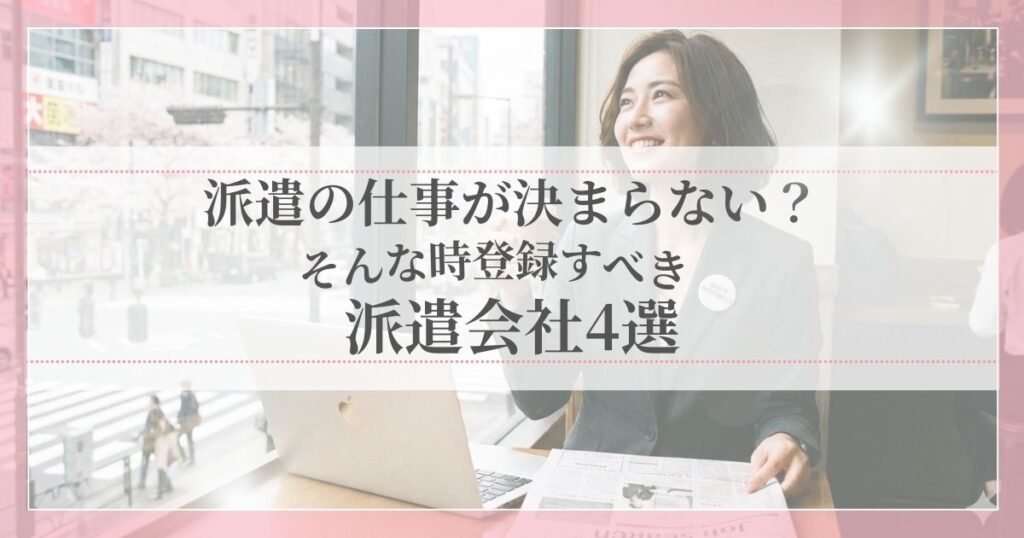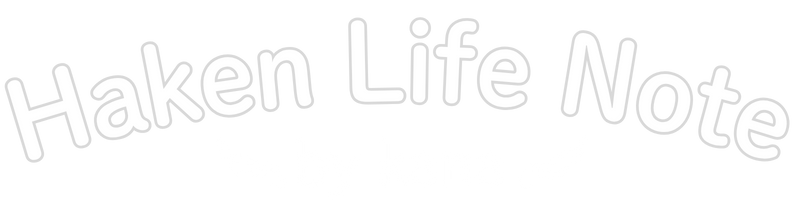【簿記3級試験対策】電卓選びで失敗しないためのポイント&練習法
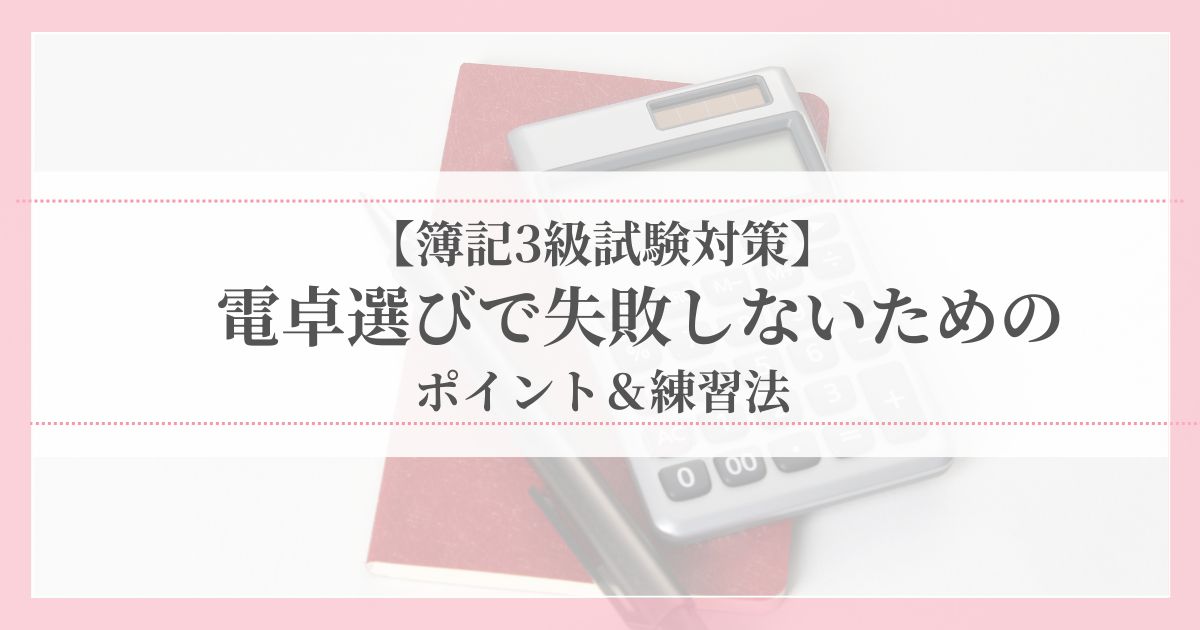
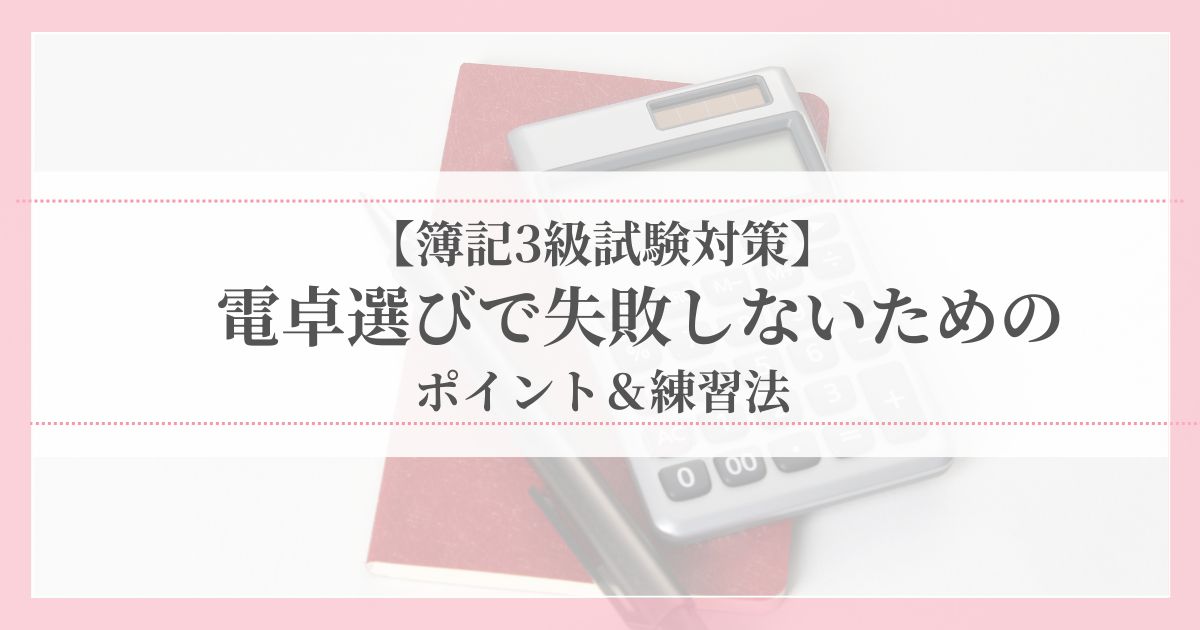
正直、電卓なんてすぐ慣れるし、どれでも一緒だろうと高をくくっていた私。
でも実際は、模擬試験や練習問題で 桁数の多い数字 を扱うようになったとたん、電卓で思わぬ苦戦を強いられました。
ちゃんとした選び方も、操作の練習もせずに挑んだ結果——
「もっと早く知っていれば…!」と後悔したポイントがたくさん。
この記事では、私が感じたつまずきポイントと、電卓選び・使い方・練習方法 をまとめます。
これから簿記検定を受ける方にとって、電卓って“意外な落とし穴”かも…!?参考になれば嬉しいです😊
簿記における電卓の役割は想像以上に重要だった
簿記検定では、ExcelのようにコピペやSUM関数は使えません。
すべて、自分の手で電卓を打っていくしかないのです。
最初は「7桁、8桁の数字をポチポチ打つだけでしょ?」と軽く思っていました。
でも実際は、その数字を10個以上足して、一発で正確な合計を出すのは至難の業…!
打ち間違い → 合計が合わない → やり直し → でもまた合わない…
そんな“電卓ループ”にハマって、試験直前まで苦戦しました😅
電卓の操作精度って、思っていた以上に簿記のスコアに直結するものだったんです。
一見簡単そうなのに…実際は“ミスなく打つ”ことがこんなに大変だとは思いませんでした😅
私が実際に電卓でつまずいたこと
電卓に慣れる時間が少なかった
勉強を始めて2週間が過ぎた頃に、ようやく電卓を買いに行ったのですが、今思えば、勉強を始めた最初の段階から購入して、早いうちに慣れる練習をしておくべきでした。
テンキーには慣れていたので「まあ余裕かな」と思っていたけれど、パソコンのキーボードと電卓の操作感は別物。
- キーの深さや押し心地
- 配列の感覚
- 指の動かし方のクセ
すべてが微妙に違っていて、打ちミスの原因にもつながっていたんです…!
安い電卓を選んで後悔した
簿記3級の受験前、ネットで調べてみると「100均の電卓でも大丈夫だった」なんて声も見かけて、「じゃあ安くていいか!」と思って、私は、シャープの1,000円以下の電卓を購入しました😭
00(ダブルゼロ)キーの有無や、12桁表示かどうかは少しだけ気にしていましたが…
実際に使ってみて不便だと気づいたのが、「桁下げキー」がなかったこと。
パソコンでいう“バックスペース”のような機能ですね。
一度に全てを消す「クリアエントリー」は使えたものの、「1桁だけ消したい…!」という場面で対応できず、かなり後悔しました。
簿記で押さえておきたい電卓の基本知識と操作
簿記の試験では、ただ数字を打つだけでなく——
“電卓の機能”を使いこなせるかどうかが、作業効率にも影響します。
ここでは、簿記に役立つ代表的な電卓機能を紹介します
メモリー機能
- M+(メモリープラス):表示されている数値をメモリーに加算して記録
- M-(メモリーマイナス):表示されている数値をメモリーから減算して記録
- RM(メモリーリコール):記録されたメモリー内容を表示
- CM(クリアメモリー):記録したメモリーを消去
グランドトータル(GT)機能
複数の計算結果を自動で合計する機能。メモリー機能に似ていますが、
「=」を押した瞬間の計算結果が自動記録され、あとからGTボタンを押すと累計が表示されます。
- GT機能が使えるように、設定スイッチをONにする必要がある機種もあります
パーセントボタン
消費税や割引計算などに便利な機能。
たとえば「10,000 × 5%」と入力すれば、すぐに「500」が表示されます。
出来たら練習しておきたい電卓テクニック
「簿記の知識を覚えるので精一杯で、電卓の練習までは手がまわらない…」そんなふうに思いますよね?
でも、電卓を効率よく扱えるだけで、計算時間や試験の余裕が全然変わってきます!
本格的に経理の道に進む予定がある方なら、このテクニックは早めに身につけておくと、きっと役立ちます📘
ブラインドタッチ
電卓にも「ホームポジション」があります。
計算前に、薬指を「4」、中指を「5」、人差し指を「6」に置くのが基本。
この位置から他のキーに指をスムーズに伸ばすことで、“画面を見ずに打つ”=ブラインドタッチが可能になります。
- 視線の移動が減る
- 打ち間違いが減る
- 時間に余裕がうまれる
試験中に“電卓と紙面を往復”しなくて済むのは、本当にラクです😊
利き手の逆で電卓を使う
これは、YouTubeの簿記解説動画で先生方がみんなやっていて、「かっこいい!私もやってみたい!」と挑戦したものです。
慣れるまではかなり難しいですが、利き手でペンを持ちながら、逆の手で電卓を打てるようになると、ペンの持ち替えが不要になり、一気に作業効率がUPします🌿
まだ完璧にはできないけど…練習してみる価値はあると思います✨
電卓おすすめ4選|目的別で選ぶならこのモデル!
実務派も試験派も「これ1択」【シャープ EL-G37】
簿記2級以上や経理・会計職を本気で目指すなら、この電卓で決まりです。
多くの資格学校や簿記系YouTuberが紹介している定番中の定番モデルでもあります。
いわゆる“学校用電卓”と呼ばれ、商業高校や専門学校、資格取得者向けに開発された信頼の一台。
- カウンターつき液晶表示(入力ミスを防ぎやすい!)
- 高速早打ち対応(試験中のスピードにも安心)
- 強化滑り止めゴム(打ち込んでもズレない安定感)
🛒 TAC出版オンライン直販サイト📍 購入はこちら
本体価格:4,700円+税(※非会員の場合:送料・手数料で+500円かかるようです)
値は張りますが、これを買えば間違いなし!
カシオ派ならこれ!ND-26S
「シャープ EL-G37」と並ぶ簿記2級・経理職向けの代表モデルです。
特にカシオの電卓に慣れている方にはおすすめ。
私は「ゼロ」の位置が「1」の下にないのがちょっと打ちづらい…と感じたのですが、
使い慣れている人なら、逆にこの配列がしっくりくるかもしれません😊
- 数字キーが中央に集約され、人間工学に基づいた設計
- 下位置に表示される「3桁区切りコンマ」で視認性◎
- 列ごとにキーの形状を変えていて、高速入力&静音&耐久性あり
📍 大原ブックストアで購入
販売価格:送料無料で約6,000円
簿記3級なら|シャープ EL-VN82-AX
簿記3級の試験対策としては、十分な機能を備えた電卓です。
上位モデル(EL-G37やND-26S)はいかにも“事務用”という印象がありますが、
このモデルはアルミパネル仕様+カラーバリエーションありで、見た目の高級感が魅力✨
4色展開で、モノとしての満足感も高いです。
「機能も欲しいけど、デザインにもこだわりたい!」という方にぴったり。
地道な簿記の勉強でもお気に入りの電卓があると、ちょっとテンション上がるかも?
シンプル派なら|無印良品 BO-192
無印らしいシンプル&ミニマルなデザインが特徴の電卓。
どんなデスクにもなじみやすくて、見た目重視派の方にも人気です。
ちなみに、【簿記・FP】独学ちゃんねるの桜田さんが使っていた電卓が気になって「これかな?」と思って見てたのですが…もしかしたらこの無印モデルかもしれません(間違ってたらすみません💦)
おまけ:電卓の練習にもなる簿記3級おすすめテキスト
簿記の勉強では、最初は3桁くらいの数字で仕訳を練習することが多いと思います。
でもそれだけだと、“電卓の打ち込み力”はなかなか身につかないんですよね…。
このテキストは、模擬試験形式の問題が多く収録されていて、桁の多い数字や複数仕訳を打つ練習を通じて、自然に電卓にも慣れていけます!
私はこのテキストを使って何度も模擬試験をこなすうちに、「電卓のスピードと正確さ」がかなり上がった感覚がありました📘✨
📚 合格するための本試験問題集 日商簿記3級 2025年SS対策
[ネット試験・統一試験 完全対応] TAC出版(よくわかる簿記シリーズ)


合格するための本試験問題集 日商簿記 3級 2025年SS対策[ネット試験・統一試験 完全対応](TAC出版) (よくわかる簿記シリーズ)
まとめ|目的に合わせて電卓も選び方が変わる!
簿記3級をこれから始める方であれば、「シャープ EL-VN82-AX」や「無印良品 BO-192」など、見た目も使いやすさも兼ね備えたモデルで十分対応できます😊
一方で、簿記2級以上や会計職を目指している方は、少し予算はかかりますが「シャープ EL-G37」や「カシオ ND-26S」のような「学校用電卓」を最初から選ぶのがおすすめ✨
後から「やっぱり上位モデルを買い直そう…」となるケースもあるので、長く使いたい・本気で学びたい方ほど“早めのいい選択”がコスパにもつながるかもしれません
高機能モデルも魅力ですが…やっぱりお財布と相談して「今の自分に合う1台」を選ぶのがいちばんですね😊
あわせて読みたい記事:
👉 派遣歴30年の私がすすめる日商簿記3級|求人・副業・家計に効く5つの理由
👉 【簿記3級】一度落ちた派遣社員が独学でリベンジ合格!勉強法とつまずきポイントを公開
👉 経理職を目指す派遣社員に!簿記2級・3級を一気に学べるWeb通信講座【クレアール】
※当ブログの内容は、管理人の実体験と主観に基づいたものです。できる限り正確な情報を心がけていますが、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。