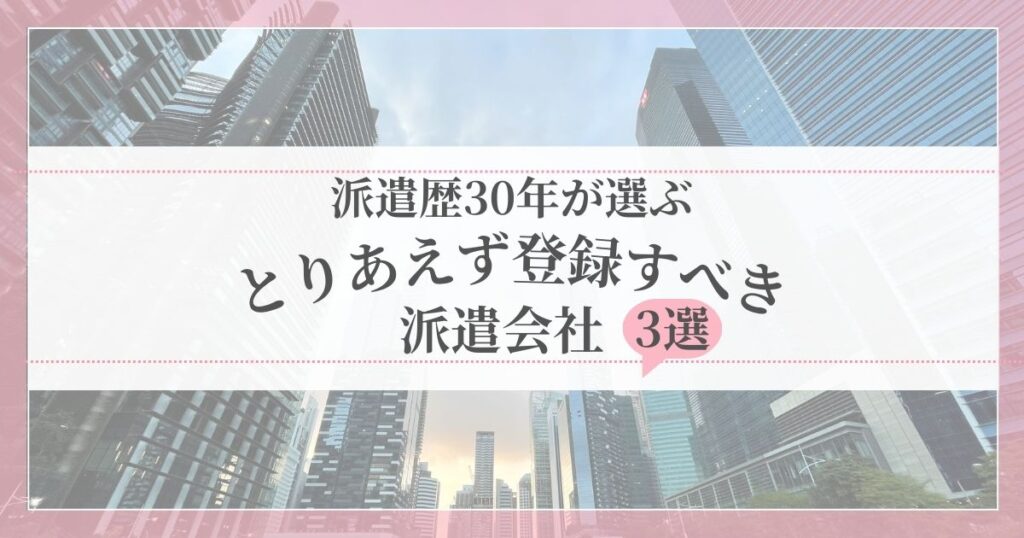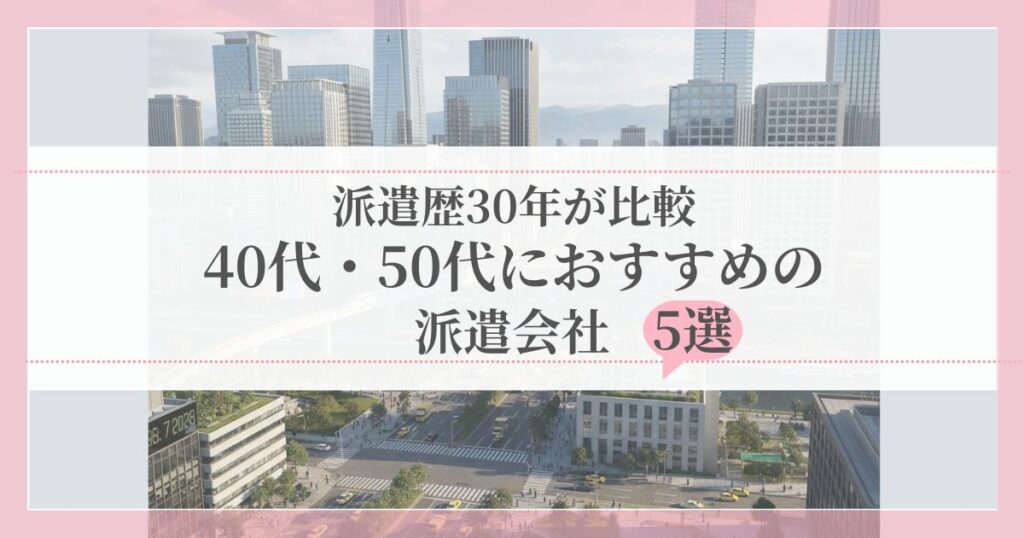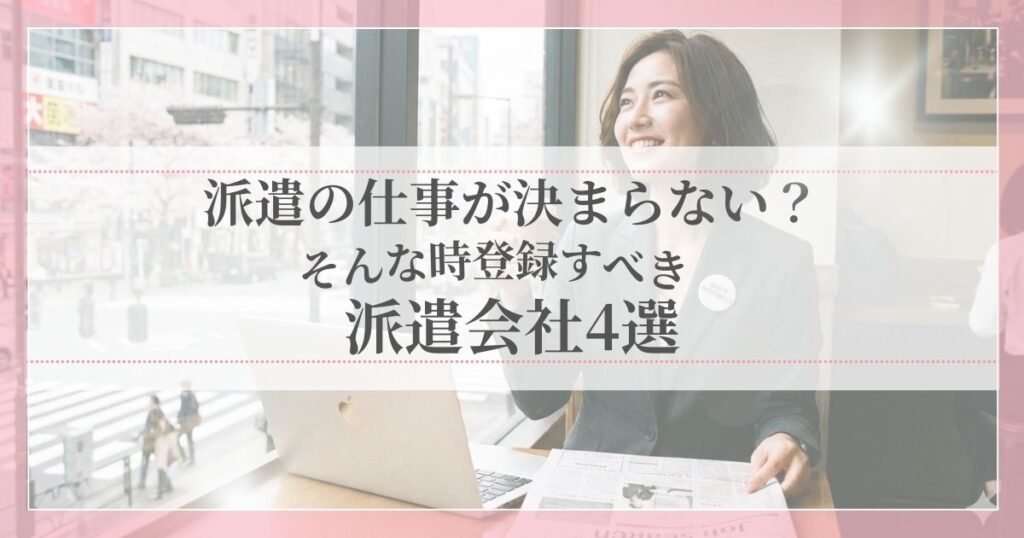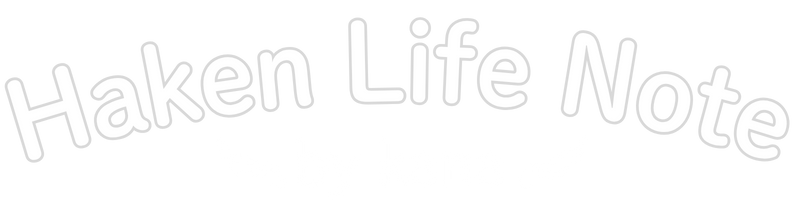【簿記3級】一度落ちた派遣社員が独学でリベンジ合格!勉強法とつまずきポイントを公開
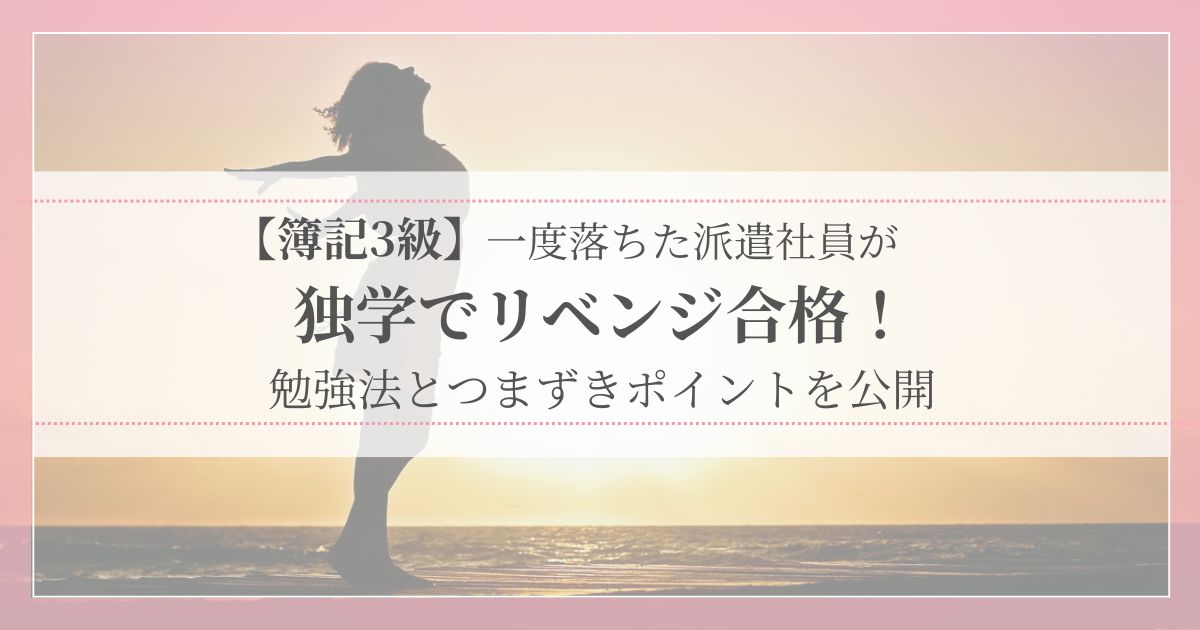
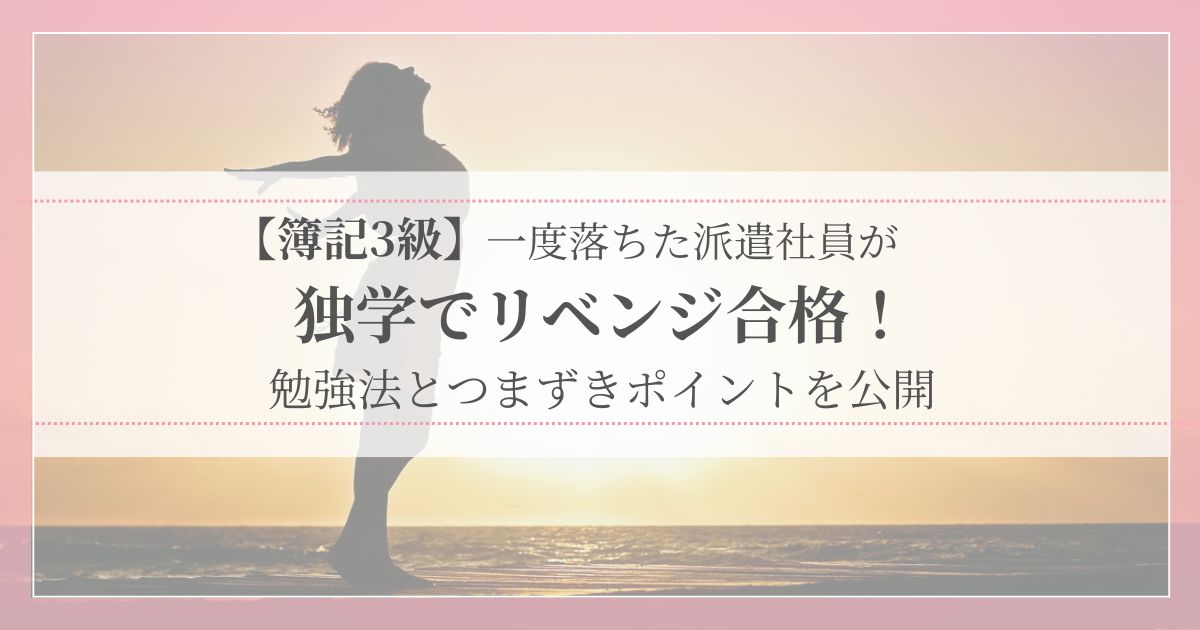
「簿記って難しそう」「経理の仕事をしないから関係ない」――私も以前はそう思っていました。
でも実際に勉強を始めてみると、ちょっと大げさですが、世の中を見る“解像度”が上がった気がします。
私は一度、簿記3級の試験に落ちました。それでもその1か月後に90点以上で、無事合格することができました。 この記事では、そんな私の体験談をもとに、「どんな勉強法をしたのか」「どこでつまずいたのか」など、リアルな声をお伝えします。
これから簿記3級に挑戦する派遣社員さんや、独学で勉強しようか悩んでいる方の参考になればうれしいです😊
なぜ簿記3級に挑戦したのか
私はよく「両学長 リベラルアーツ大学」のYouTubeを見るのですが、そこで両学長が「簿記取りや~」とよくおっしゃいます。それで気になっていた簿記3級。Kindle Unlimitedで簿記のテキストを覗いてみたものの、「とても無理!」って思って放置していました。
それなのに何故、勉強を始めたかというと、派遣のお仕事のブランク期間が思ったより長くなってしまった時期があり、「この期間を利用して1か月で取得してしまおう!」と思ったのがきっかけです。
簿記3級に合格するために必要な勉強時間の目安は一般的に100時間程度と言われています。働きながらだと私には厳しいと思い、勉強にとりかかることにしました。
この期間をただの空白ではなく、何か意義あるものにしたかったのです。
日商簿記3級の試験内容(ネット試験)
- 試験時間:60分
- 受験料:3,300円+事務手数料550円(税込)
- 受験資格:どなたでも受験可能
- 合格基準:100点満点中70点
詳しくはこちら(公式サイト)👉 日本商工会議所|日商簿記検定
| 出題傾向 | 配点 | |
|---|---|---|
| 第1問 | 仕訳形式で解答を求められる問題15題が出題 | 45点 |
| 第2問 | 補助簿に関連する問題、取引勘定に記入する問題や文章の空所補充問題などが出題 | 20点 |
| 第3問 | 財務諸表(損益計算書・貸借対照表)、精算表や決算整理後残高試算賞の作成問題が出題 | 35点 |
簿記3級は、業種・職種を問わず、ビジネスパーソンが身につけておきたい「必須の基本知識」として、多くの企業から評価されている資格です。
基本的な商業簿記を学び、小規模企業の経理実務や企業活動を理解したうえで、帳簿や領収書などの書類を正しく処理する力が求められるレベルです。
多くの簿記の先生が「第1問 → 第3問 → 第2問」の順に解くのをおすすめしています。
私もこの順番で取り組みましたが、確かにこの順番だと時間配分がしやすくて、落ち着いて見直しする余裕もできました。
【体験談】私の独学勉強法
最初の1か月の勉強法
私の目標は、「1か月で、お金をかけずに簿記3級に合格すること」でした。
まずは【簿記系YouTuber?】ふくしままさゆきさんのYouTubeとテキストで勉強しました。 私は、Kindle Unlimitedに加入していたので、テキストも無料。
YouTubeとテキストが同じ構成なので大変便利でした。
- YouTubeを見て概要欄の問題を解く
- テキストを読んで例題を解く


ホントにゼロからの簿記3級 『ふくしままさゆきのホントに』シリーズ
この流れでまず25本ある動画を1周しました。
ふくしまさん曰く「25本のYouTubeを3周せよ」とのこと。
しかし私は、後半にいくにつれついていけず、ふくしまさんの「簡単でしょ?」「簡単ですね。」の言葉に次第に心削られ、別の動画も見ることにしました。
(あとで改めて動画を見返したときは、まったく嫌味に聞こえなかったんですよね。あまりにも分からなさすぎただけでした……😓)
次に視聴したのが「【簿記・FP】独学ちゃんねる 桜田」さんの動画。とても綺麗に作り込まれていて、優しい語り口と丁寧な解説が印象的でした。
動画の最後に勘定科目の5要素の復習が入っている点も、理解の助けになってとてもわかりやすかったです。
桜田さんの動画も1周視聴し、それぞれに登場する仕訳問題に取り組みました。
「まだ苦手だな…」と感じた論点については、ふくしまさんや桜田さんの動画を繰り返し見ることで、少しずつ理解を深めていきました。
その後、以下の無料ネット模擬試験を3回分×2回実施:
模擬試験の結果は、だいたい70点前後のギリギリ合格。
60点台になることもあれば、運が良ければ80点台という感じの不安定な状態でした。
何度か模試に取り組み、解説動画も見ましたが、「問題によっては受かるかも…もうこれは運任せかな」
そんな気持ちで試験の申し込みをしました。
一度目はなぜ落ちた?リアルな失敗談
第1回目テストの体験談
試験会場の場所で迷ったら困ると思い、かなり時間に余裕を持って出発しました。
実際には迷うことなく、予定よりずっと早く到着。
それでも、待たされることなく受付を済ませることができました。
荷物はロッカーに預け、そのまますぐに試験を始める流れに。
試験中は机の上に本人確認証を置き、持ち込みできるのは電卓だけ。
メモ用紙とボールペンは受付で受け取り、試験後に返却します。
初めての場所での初めての簿記試験。静かな会場で、張り詰めた空気の中、私はかなり緊張していたと思います。
試験問題は、模擬試験の経験上、ひねった内容が少なく、比較的悩まずに取り組めました。
時間もわりと余裕があり、落ち着いて解答できたように思います。
第3問は、損益計算書と貸借対照表を作成する問題でしたが、私にしては珍しく左右の合計が一致!
「これは合格かも……」と、淡い期待を抱きました。
結果は……66点で不合格😭
- 第1問:39点(2問も間違ってた……)
- 第2問:7点(ここはほぼ捨ててたので、仕方ない)
- 第3問:20点(貸借対照表の合計、合ってたのに😱)
難しいと感じる問題はなかったのに、惨敗……。ショックでした。
\試験会場で気になったこと/
- ネット試験ならではですが、途中で人が入ってくるので、ちょっと気になることも。
- キーボードがカチャカチャいうタイプで、それを壊れるかってくらい強く叩く人がいたり、大きなため息をつく人もいて…集中するのが少し大変でした。
振り返ってみると、緊張と慣れない環境で、かなり冷静さを失っていたと思います😓
原因①:基礎の土台の弱さ
一通りの論点は頭に入っていたつもりでしたが、少しでも応用になると急にわからなくなってしまって、
「まだまだ基礎が脆くてグラグラな状態だったな…」と今では思います。
頭では理解していたつもりでも、逆に仕訳してしまうようなケアレスミスも多い状態でした。
たとえ3級でも運任せでは、合格できないと痛感しました。
原因②:電卓に不慣れ
YouTubeでは論点理解のために、100円とか3桁程度の金額を使って解説されていました。
でも、実際の試験問題では100万や1000万といった大きな金額が普通に出題されます。
Excelに慣れきっていた私は、数字といえばコピペが当たり前。
電卓で万単位の数字をひとつひとつ打つことに慣れていなくて、桁を間違えることがよくありました。
合計も、もちろんSUM関数なんて使えません。
10個以上の数字を地道に足していく作業は、最初は「これほぼ不可能では…」と感じるほど大変でした。
勉強を始めてしばらく経ってから電卓を買いに行ったのですが、「すぐ慣れるだろ」と思っていたのは甘かったです。
今思えば、最初から購入して、操作に慣れる時間も含めておくべきでした。
ちなみに私は、安さ重視で800円台の電卓を選んでしまったのですが…
「桁下げキー(1字だけ消せる機能)」がないのが意外と不便で、後悔しました。
あわせて読みたい記事:
👉【簿記3級試験対策】電卓選びで失敗しないためのポイント&練習法
原因③:第2問を捨てたのは失敗
第1問の仕訳問題は、パーフェクトを目指すべきところです。
ただ、慣れない試験会場の雰囲気で冷静さを欠き、簡単なミスをしてしまう可能性もあります。
そうなると、第2問での部分点が合否を左右することになります。
配点は20点とはいえ、もう少ししっかり勉強しておくべきだったと感じました。
不合格後の勉強法(2か月目)
本試験問題集を1冊やり込むだけ!
不合格になった傷心のまま、帰りに書店へ立ち寄り、
『合格するための本試験問題集 日商簿記3級 2025年SS対策[ネット試験・統一試験 完全対応](TAC出版/よくわかる簿記シリーズ)』定価:1,870円(本体価格+税)を購入しました。


合格するための本試験問題集 日商簿記 3級 2025年SS対策[ネット試験・統一試験 完全対応](TAC出版) (よくわかる簿記シリーズ)
「もっと模擬試験の場数を踏むべきだった」——
無料のネット模擬試験6題では、私には足りなかったのだと思います。
次の日からは、この問題集1冊だけを使って勉強することに。
この問題集は前半に、第1・第2・第3問それぞれの対策問題と解説があり、後半には、筆記形式の模擬試験が12回分とその解説が掲載。さらにネット試験形式の模擬試験も10回分ついています。
私は順番に問題を解いていき、間違ったところには付箋を貼り、何度も解き直して「もう大丈夫」と思えたら付箋を外す——そんなふうに復習していきました。
それが終わると、12回分の筆記模擬試験に取りかかり、自分で採点し、間違えた箇所はわかるまで繰り返して復習。
この12回分の模試をやり切ることで、基礎力がぐっと定着し、ケアレスミスもずいぶん減ってきました。
そして仕上げにネット試験形式の模試10回分に挑戦。
すべて合格点を取ることができたので——再挑戦を決意しました。
第2回目テストの体験談
前回と同じ試験会場だったこともあり、受付の流れや会場の雰囲気がわかっていた分、ずいぶん緊張せずに済みました。
いよいよ試験本番。
第3問の決算整理仕訳はけっこうひねりがあって、「ここ間違ってたら、いろんなところに影響出るかも…」
そう思うほどに、どんどん自信がなくなっていきました。
第2問は、備品の減価償却に関する仕訳と、どの帳簿を使うかを選択する問題。
こちらも確信が持てず、さらなる不安が…..。
時間には余裕があり、見直しも何度かして、それでも時間が余っていました。
でも、「試験終了」のボタンを押す気にはどうしてもなれず…
「あぁ…またダメだったのかも。またここに来て、3回目の試験を受けることになるのかな……」
そんな気持ちのまま、試験終了時刻をただじっと待ちました。
結果は……
93点合格😆✨
- 第1問:45点(パーフェクト!)
- 第2問:20点(まさかのパーフェクト!!)
- 第3問:28点(もう少し取りたかったけど、難しかったから納得)
嬉しさと安堵感で胸がいっぱいになり、ロッカーから荷物を取り出す手が震えていたのを、今でもはっきり覚えています。
目標通り「1か月&お金をかけずに合格」とはなりませんでしたが、
1度落ちたことで基礎固めができたので、結果的にはヨカッタと思うようにしてます😓
簿記3級は独学でOK!失敗から学んだおすすめ勉強法
1. YouTubeを活用
同じ動画を繰り返し3周視聴するのは、正直飽きてしまって私には無理でした。
- 【簿記系YouTuber?】ふくしままさゆきさん:1周視聴
- 【簿記・FP】独学ちゃんねる 桜田さん:1周視聴
それぞれの仕訳問題の動画を解きながら視聴し、
苦手な論点はどちらか、または両方の動画を繰り返し見ることで理解を深めました。
私はどちらの動画もノートを取りながら視聴し、自分なりにまとめていました。
2. 無料ネット模擬試験に挑戦!
これらのネット模擬試験(全6回)で、すでに 80〜90点台を安定して取れている人 は、試験に申し込んでも合格できる可能性が高いと思います。
ただし、
- ギリギリの合格点(70点前後)が続いている人
- 一度で確実に合格したいと思っている人
そんな方は、次の「3. 本試験問題集に取り組む」 に進んで、さらに対策を重ねることをおすすめします!
3. 本試験問題集に取り組む
『合格するための本試験問題集 日商簿記3級 2025年SS対策[ネット試験・統一試験 完全対応](TAC出版/よくわかる簿記シリーズ)』
とにかくこの問題集を、最初からじっくり解きながら進めていきます。
間違えたところには何度も挑戦し、「自信あり」と思えるまで繰り返し復習。
仕上げにはネット試験形式の模擬問題10回分に挑戦し、ほぼすべてで合格点を取れたタイミングで、試験を申し込みます。


合格するための本試験問題集 日商簿記 3級 2025年SS対策[ネット試験・統一試験 完全対応](TAC出版) (よくわかる簿記シリーズ)
この問題集の定価は 1,870円(本体+税)。
不合格になると、受験料3,300円+事務手数料550円(税込)が再度かかります。
それを考えると——
この問題集は、買って損なし!です。
私はこの問題集を通じて、基礎力がしっかり身につきました。😊
4. 第2問が苦手な人に効く!おすすめの動画
第2問は、配点が20点と比較的低めなのに、出題範囲が広すぎて、
「何を勉強すればいいかわからないし、もう捨てようかな…」と思ってしまいがちですよね。
1.の模擬試験解説を見たり、3. の問題集でだいぶ慣れてきても、試験では何が出題されるのか、やっぱり不安は残るものです。
そこで、「第2問は捨てようかな…」と迷っている方に向けて、部分点を数点でも確実に取れる可能性がある動画をご紹介します!
この動画では、主要簿・補助簿をそれぞれ幅広く解説してくれて、第2問のコツを教えてくれます。
例えば、資産・負債・純資産の帳簿には「次期繰越」「前期繰越」が、費用・収益には「損益」がくる——
この部分だけでも知っていると、部分点を狙える可能性が十分あります。
📺 試験直前にでも、ぜひ見ておきたい動画です。
独学が苦手、簿記2級を目指す人にはWebスクールもあり
「一人で勉強するのが苦手…」「簿記2級も視野に入れている」という方には、もう少し体系的に学べる環境が欲しいと思うかもしれません。
そんな方には、Webスクールの受講もおすすめです。
- 3級講座は1万円代など、他社と比べてリーズナブルな価格設定
- 質問は無制限で、サポート体制がしっかりしていて安心
- 3・2級講義パックで効率よく学べる
このようなコスパの良いスクールもあるので、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか?
おすすめWebスクールはこちら👇
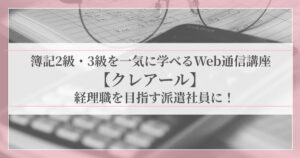
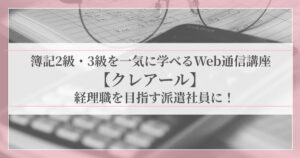
まとめ
簿記3級は、独学でも十分に合格できる資格です。
でも——「理解したつもり」では合格できない資格でもあります。
一度不合格を経験したからこそ、
根気よく、あきらめず、着実に復習して“基礎をしっかり築く”ことがなにより大切だと感じました。
「自分が持っているカード」をもう1枚増やすつもりで、簿記3級に挑戦してみませんか?
持っているカードは多ければ多いほどチャンスは広がります😊
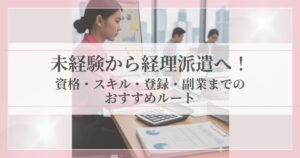
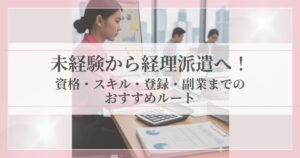
※当ブログの内容は、管理人の実体験と主観に基づいたものです。できる限り正確な情報を心がけていますが、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。