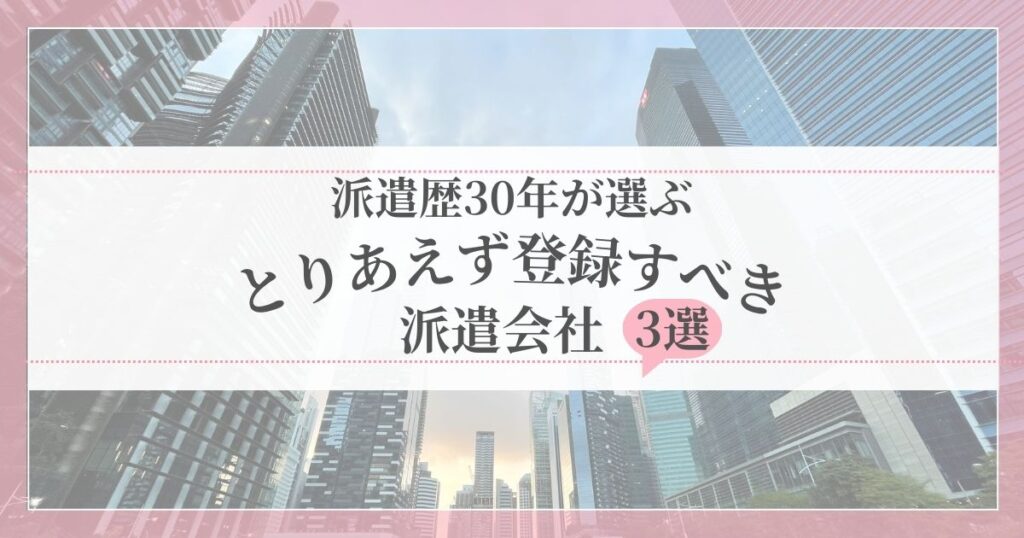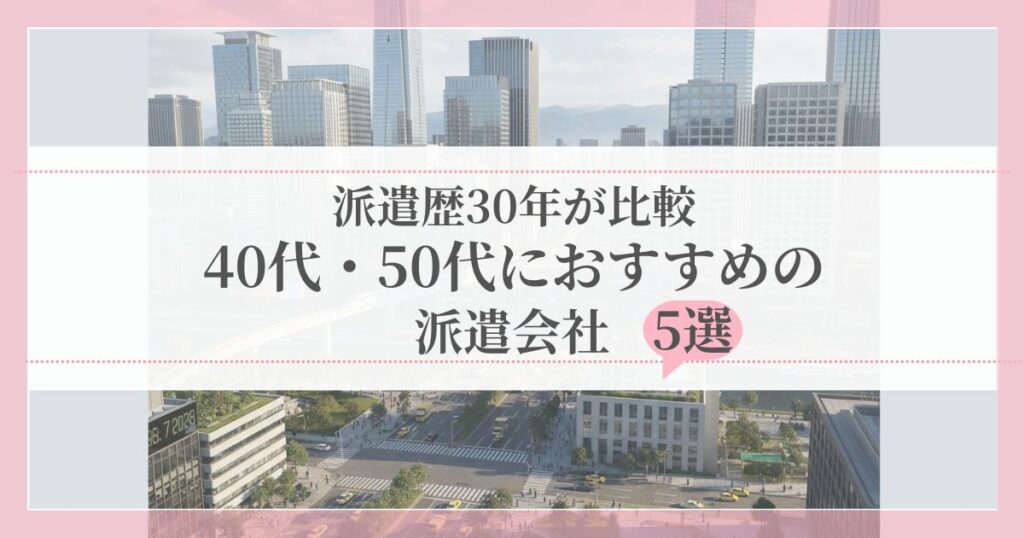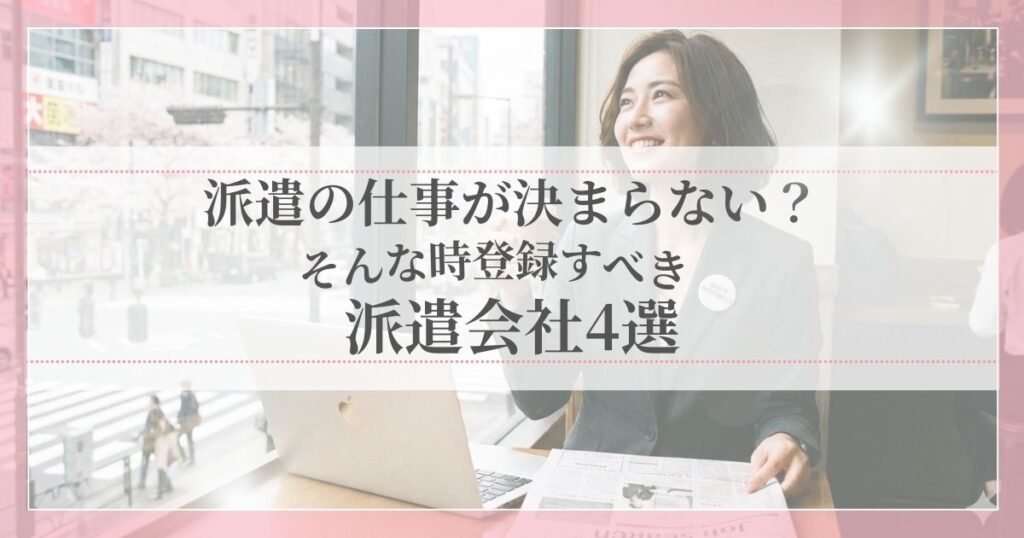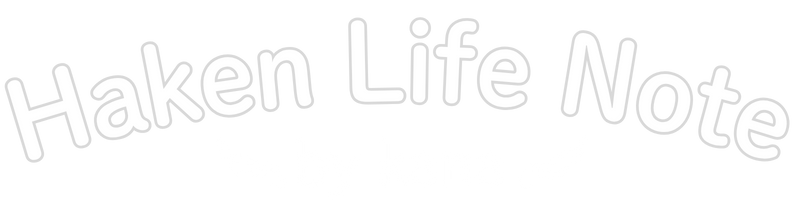派遣社員の本音|職場のお土産文化が面倒に感じる理由と私のルール


職場のお土産文化、ちょっと面倒だな…と思ったことはありませんか?
気にしていない人もいるかもしれませんが、出張や休暇のたびに「必ず買ってくるのが当然」という雰囲気が残っている職場もあります。
最初は「もらえて嬉しい」だったはずのお土産も、頻繁になると気を使うだけになったり…。
買う側にとっても、せっかくの旅行中に「何を買うか」で悩むのは負担です。
派遣社員だと「配る係」にされることも多く、正直うんざりした経験を持つ人も少なくないはず。
今回は、そんな「職場のお土産文化」について、派遣歴30年の私が感じてきた本音をお話します。
私は、お土産文化…かなり苦手派です💦
同じように「ちょっと面倒だな」と感じている方に、共感してもらえたら嬉しいです😆
お土産文化の由来と職場に根付いた理由


お土産文化の始まりは、神社やお寺への参拝にあります。昔は参拝の証として授かった品を、家族や地域に「おすそ分け」するのが原型でした。
江戸時代には伊勢参りなどが庶民の間で広まり、特産品を村へのお土産として持ち帰る習慣が定着。「旅の報告」としての意味合いも強かったようです。
現代の職場では、お土産は「休暇や出張で留守にしたお詫び」や「感謝の気持ち」を表すものとして扱われています。
日本社会に根強い「調和」や「気配り」の意識もあり、自然と職場文化として残ってきた背景があります。
ただし近年では、費用や選ぶ・配る手間を負担に感じる人も増えています。
「お土産は不要」とルール化する会社も出てきましたが、まだまだ多くの職場では根強く残っているのが現状です。
ちょっとした気遣いのはずが、いつの間にか“義務”っぽくなってしまった…それが今のお土産文化なのかもしれませんね😢
職場のお土産文化に感じるモヤモヤとプレッシャー


お正月休みやお盆明けの電車では、お土産袋を下げた人をよく見かけます。
いまだに根強く残る、お土産文化。
私は派遣でひとり暮らしなので、金銭的にも余裕があるわけではなく、旅行もそれほど好きではありません。
そのため、職場では「もらうばかり」になってしまうことが多く、課内で自分だけお土産を配らなかった…ということも何度かありました。
たまに旅行に行ったとしても、みんなに配ることはほとんどありません。
ちょっと肩身が狭い気もしますが、「その時だけのこと」と割り切って、気にしないようにしています。
(…お土産文化への、ささやかな抵抗??😅)
また、席を外していた時に机にお菓子が置かれていることもあります。
誰からのものかわからず、周囲に「このお菓子、どなたからですか?」と聞いて、お礼を言いに行く…。
個包装ではなく、紙ナプキンにそのまま置かれていたりすると、衛生面も気になりますし、「今は食べたくないのに…」と感じることも。
そのまま置いておくと干からびてしまいそうで、なんだか気を使ってしまいます。
本来は「ちょっとした気遣い」であるはずのお土産も、義務化されてしまうと、
強制的に受け取らされて、お礼を言わされているような気分になってしまうこともあります。
買う側も、実はかなりのプレッシャーを感じるものです。
誰に渡すか、何個入りがいいか、どのお土産屋さんで買うか、いつのタイミングで買うか…。
せっかく仕事を忘れてリフレッシュしに来ている旅行なのに、そんなことで時間もお金も使って悩まなくてはならないなんて、ちょっと本末転倒ですよね。
ネットで調べてみると、お土産文化に対する意見は賛否両論です。
「旅行自慢に感じる」「気を使わせてしまっているみたい」(読売オンライン)「あの人は貰ってばかりで買ってこない」など、さまざまな声があります。(発言小町)
仕事してるだけでも十分ストレスなのに…
お土産で心を煩わせるなんて、ちょっとしんどいですよね。
この文化、そろそろ見直してもいいのでは?と感じませんか?
「配らされる側」の負担とモヤモヤ


派遣社員だと、なぜか「お土産配る係」になってしまうこと、ありませんか?
当然のように「これ、配っておいて」と渡されて、気づけば自分が配る役回りに。
だいたい、こういう雑務は派遣社員にまわってくることが多い気がします。
「ただ配るだけじゃん」と思われるかもしれませんが、実はけっこう気を使うんですよね。
個数がグループ分では余るし、かといって課全体分は足りない。
個包装ならまだしも、海外のお土産などで区切られているだけのものだと、一個ずつ切り離して、紙ナプキンに触れないように置く…なんて手間もかかります。
「〇〇さんからです」と言いながら配るのも、正直あまり好きではありませんでした。
仕事しているほうが、ずっと気が楽です。
最近では、共有スペースに「ご自由にどうぞ」とメモを添えて置くスタイルが定番になってきて、個人的にはすごくありがたいなと感じています✨
無理しないための私なりのルール


以前は、私自身も所属グループの人にお土産を配っていたことがあります。
でも最近は、まったく配っていません。
退職時のお菓子も、気分で配ったり、配らなかったり。
「こうするべき」といった義務的なことは、もうやりたくありません。
その代わり、すごくよくしてもらっている方や、休暇中に業務を代わってくれた方などには、個別に渡すようにしています。
そのほうが、より良いものを選べますし、感謝の気持ちもきちんと伝わるように感じます。
「みんなに配らなきゃ」ではなく、「渡したい人に渡す」。
そのほうが、もらう側も、渡す側も、嬉しいと思うのです✨
義務じゃなくて、気持ちで渡す。
そんなお土産なら、きっと“感謝”がちゃんと届く気がします😊
まとめ|お土産は義務じゃなく気持ちでいい
「たかがお土産、なんでもいいんじゃない?」と思う一方で、
ちょっとした気遣いだったはずのものが義務化され、負担に感じる人が多くいるのも事実です。
最近では「お土産禁止」としている企業も増えてきていて、これはとても良い傾向だと感じます。
そもそも会社は、お友達を作りに行く場所ではなく、仕事をしに行く場所です。
「お土産を買わないと気が利かないと思われる」なんてナンセンスです。
マネージャー層が「たかがお土産に負担を感じている人がいる」と気づいて、
「お土産は不要です」と一言伝えてくれるだけで、職場のモヤモヤはずいぶん解消されるはずです。
バレンタイン文化が少しずつ廃れてきたように、お土産文化もいずれなくなるのかもしれません。
そういったつまらない「気遣い」に振り回されることなく、
純粋に“仕事そのもの”で評価される職場が、もっと当たり前になっていくといいなと思います。
こういう日々のモヤモヤの積み重ねが、「なんか面倒…」「会社行きたくない…」に繋がっていく気がします。
一見些細なことでも、モヤモヤは少しずつ減らしていきたいですね😊
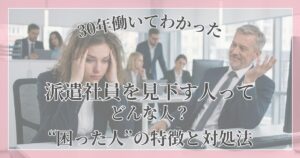
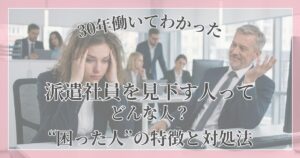
※当ブログの内容は、管理人の実体験と主観に基づいたものです。できる限り正確な情報を心がけていますが、最終的なご判断はご自身でお願いいたします。